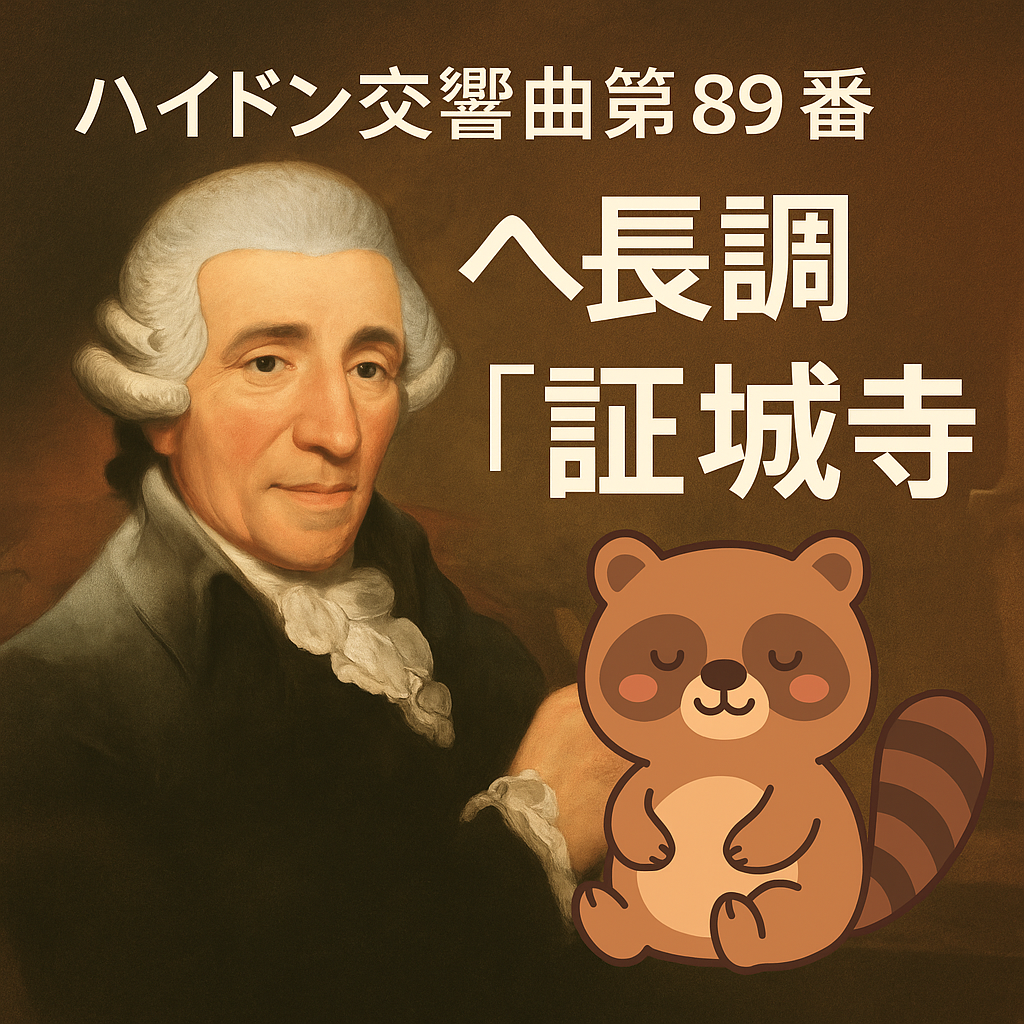みなさん、「証城寺の狸囃子」通称「しょうじょう寺」という童謡、ご存知ですよね?
そう、あの「しょ、しょ、しょうじょうじ。しょうじょうじの庭は…」というあれです。
楽しい歌ですねぇ。
ハイドンは御存知の通り終生交響曲を様々な実験を繰り返しながら作り続け、偉大にしていった大作曲家です。まさに、交響曲の父。そのハイドンの交響曲第89番は、後のベートーヴェンを予感させるという名曲です。その冒頭を、お聞きください。
分かりました?のっけから「しょ、しょ、しょじょじっ!」
まぁ、ド・ミ・ソミド、ですからね。しかし、最初に聞いたときはあっけに取られましたね。みなさんはいかがでした?でも、とても良い曲なので、ぜひ全曲聞いてみてください。
ハイドン交響曲第89番ヘ長調:古典派の成熟が響く名作
オーストリアの作曲家ヨーゼフ・ハイドン(1732–1809)は、「交響曲の父」と称されるほど、交響曲というジャンルの発展に大きく貢献しました。その中でも、1787年に書かれた《交響曲第89番ヘ長調 Hob.I:89》は、ハイドン中期の充実した創作期を代表する傑作です。
作品の背景:パリ交響曲の延長線上に
第89番は、1785年の「パリ交響曲」第82番〜第87番に続く作品として位置づけられます。実際、この第89番と第90番は、しばしば「パリ交響曲の追加2作」として扱われることもあります。ハイドンは当時、エステルハージ侯の宮廷楽団で活動していましたが、国外からの注文や出版も増え、ヨーロッパ中に名声を高めていました。
構成と音楽的特徴
第89番は4楽章構成の典型的な古典派交響曲ですが、その内容は豊かで、驚きや遊び心に満ちています。
第1楽章:ヴィヴァーチェ(Vivace)
堂々としたファンファーレ風の主題、あの「しょ、しょ、しょじょじ」で始まり、すぐに軽やかで対照的なモチーフが続きます。ソナタ形式に則りながらも、変奏や対位法を駆使して、ハイドンらしい機知に富んだ展開を聴かせます。
第2楽章:アンダンテ・コン・モート(Andante con moto)
この楽章は特に注目すべきです。変奏形式で書かれており、主題に続いて、管楽器が活躍する変奏が展開されます。オーボエとファゴットの対話や、弦と木管の色彩豊かなやりとりが聴きどころ。優雅さとウィットが絶妙にバランスしています。
第3楽章:メヌエット(Menuet)とトリオ
古典派らしいメヌエット楽章ですが、拍の位置を錯覚させるようなリズム処理や、意表を突くフレーズの切り返しがあり、単なる舞曲にとどまらない構成力が光ります。トリオではフルートと弦が牧歌的な雰囲気を醸し出します。
第4楽章:フィナーレ(Vivace assai)
陽気でエネルギッシュな終楽章。狩りのホルンのような主題が繰り返され、次々に展開していきます。明朗快活なフィナーレは、まさに「ハイドン節」の魅力全開です。
聴きどころと魅力
- ウィットに富んだ構成:突然の転調やリズムの遊び、予想外の静寂など、ハイドンらしい「驚き」が随所にちりばめられています。
- 木管の活躍:特に第2楽章では、オーボエやファゴットがソリスティックに扱われ、弦楽器との対話が魅力的です。
- 明るく親しみやすい旋律:全体にわたって調性が明るく、旋律が耳に残りやすいのもこの曲の特徴です。
おすすめの録音
- トレヴァー・ピノック指揮/イングリッシュ・コンサート
ピリオド楽器による歯切れの良い演奏。ハイドンの機知が明快に伝わります。 - アダム・フィッシャー指揮/オーストリア=ハンガリー・ハイドン・フィル
全集録音の一部で、丁寧でバランスの取れた演奏。(上記のYouTubeがそれです)
まとめ:親しみやすくも奥深い交響曲
交響曲第89番は、派手さはないものの、ハイドンの職人的な技術とユーモア、そして豊かな表現力が詰まった佳品です。初めてハイドンを聴く人にも、古典派の魅力を再確認したい人にもおすすめできる作品です。ぜひ一度、じっくり耳を傾けてみてください。
音楽関連記事
- 年末のご挨拶: フォーレ『楽園にて〜レクイエム op.48より』ーAndrew Nashを偲んで
- ジョルダーニ「Caro mio ben (愛しい人よ)」の成立背景、歌詞、おすすめの演奏
- アニメ史に残る異色の主題歌 — 『Lilium(白百合)』ラテン語歌詞の秘密
- VTuber 町田ちまさんの Lilium と Caro mio ben
- バッハ「トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565」はもとはバイオリン曲?
- 季節のご挨拶〜バッハ:シチリアーノ(フルート、スピネット)
- ヴァイオレット・エヴァーガーデンの舞台で「みちしるべ」
- おすすめの隠れた名曲〜ダマーズ:フルート、オーボエ、クラリネットとピアノのための四重奏曲
- 季節のご挨拶〜J. S. バッハ: 羊は安らかに草を食み(フルート、ピアノ、スピネット、マリンバ)
- 今年もお世話になった方々へのご挨拶〜Fauré: Pie Jesu